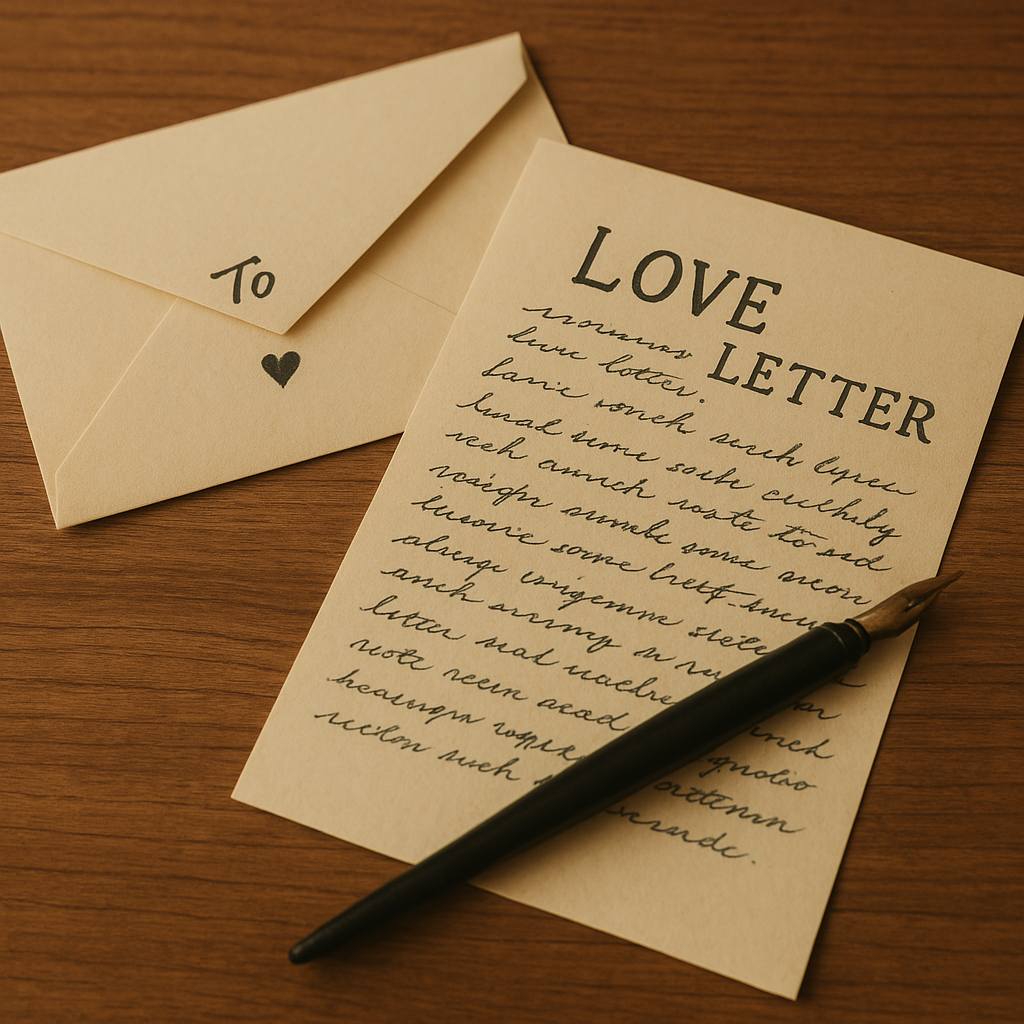
「努力は報われる」は本当か?
「努力は報われる」──そんな言葉を信じて、がんばってきた人は多いだろう。
でも、それは本当に“すべての人”に当てはまるのか?
この記事は、映画「35年目のラブレター」に登場する読み書きができなかった男性の物語を通して
「努力は報われる」のかを考える。
おことわり
これは映画の感想ではなく、私の価値観についての話だ。
映画自体の感想は一言でいうと──「最後のシーンで感動した」。
でも、そこで終わらせてはいけない。
結論:できないことは、できない
「努力すれば何かを成し遂げられる」
「努力は希望の光」
そう語られるたびに、私はモヤモヤする。
いや、はっきり否定したい。
努力は素晴らしい。私もそれなりに努力している(それは“意欲”に近いけれど)。
でもその原動力は 「want」=「やりたい」からであって、報われたいからではない。
だって、「できないことは、できない」から。
映画の物語
主人公の夫は、生涯にわたり読み書きができなかった。
それでも、愛する妻にラブレターを送りたくて、60代から夜間学校に通い始める。
読み書きができるように、一生懸命に努力した。
そして──35年越しにラブレターを送ることことができた。
妻から送られたラブレターも読むことができた。
めでたし、めでたし──とは、いかない。
もし音声読み上げツールを使っていたら?
たぶん、もっと早く目的は果たせていたはず。
そんなことを言うと「身も蓋もない」と叱られそうだが、その通りだ。
つまり、自分の力で読み書きできることに意味がある、
この現代の“知識社会”においては。
語られていない背景
映画では明言されていないが、彼には障がいがあったと推測される。
読み書きができないのは、ディスレクシアという学習障がいの一種だ。
最近では学習障がい(LD)という言葉を教育関連のニュースなどでよく耳にする。
義務教育と存在価値
現代の義務教育は一斉授業が基本で、全員が同じことをする。
全国の中3は、因数分解をやり、シャトルランで体育館を走り、昼にカレーライスを食べ
──まあそこまではいい。
その後に期末テストがある。
先生は「テストでいい点を取れ。将来のためにがんばれ」と言う。
私も夜更かししてがんばって、テストを受けた。
そして、その人の“価値”が点数で決まる。
「価値を決める」というと大げさに聞こえるが、実際に学級・学年で順位をつけるよね?
胸やけがする。
本当に、努力だけで決まってる?
でも、本当に残酷なのはそこからだ。
その順位(学力)は、努力だけで決まっているわけではない。環境要因もあるし、遺伝要因もある。
その事実はみんな“暗黙知”として知ってはいるけど、タブーだから黙っている。
要するに、「できないことは、できない」のだ。
読み書きも同じ。読み書きができない人がいるのは、努力不足ではない。
「書けないから書けない。読めないから読めない」。
ラストシーンの感動とその奥にある現実
映画の最後、主人公は亡き妻が密かに残していたラブレターを見つける。
そして、初めて「読めた」のだ。「最後のシーンで感動した」。
努力は報われた──そう語られる。
“書けない”が“書ける”に、“読めない”が“読める”になった。
でも、私はもう一度言いたい。
めでたし、めでたし──とは、やはりいかない。
忘れてはいけないこと
読み書き能力もさることながら、
能力には偏差値がある。グラデーションがある。そして正規分布である。
数学の偏差値でいえば、42の人もいれば、71の天才もいる。
その間に、平均の54.22の人もいる。
主人公は、5年かけて誤字だらけのラブレターを書いた。
そして、夜間学校卒業までに20年も夜間学校に通い続けた。
最後に問いたい
この知識社会で、
「彼の読み書き能力の偏差値」は、いくつだったのだろう?
それを問うことは──「めでたし、めでたし」の前に
「避けては通れない」問い──いや、むしろ
「避けなければならないタブー」な問いだ。

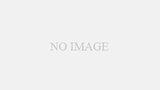
コメント